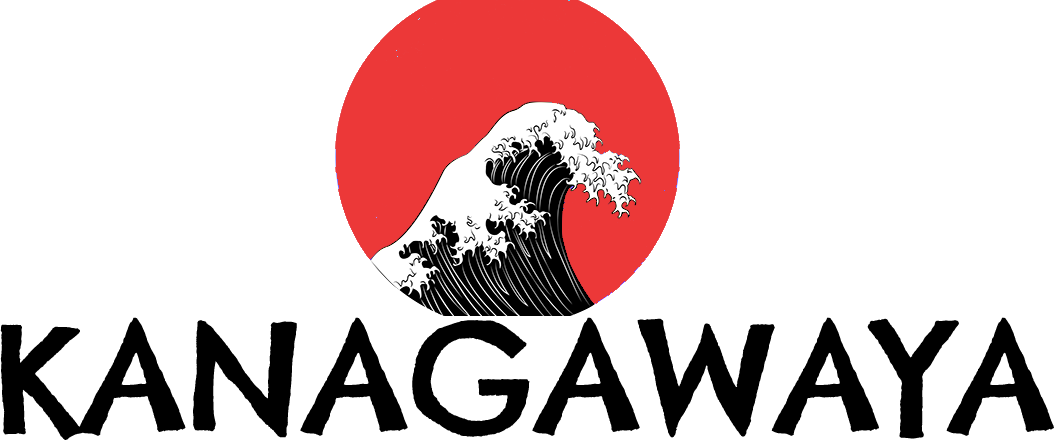お金が鍵。
最新の投稿

ドナルド・トランプ氏が自ら経営するアトランティックシティのカジノを破産させた背景
ベラジョンで使える入金不要ボーナスをゲットしよう。
トランプ元大統領が自ら経営するアトランティックシティのカジノを破産させたこと自体はかなり大きなニュースとなったものの、彼はそこからもお金を搾り取りました。ビジネスマンとしてよく知られたアメリカ元大統領のトランプ氏は、アトランティックシティにある世界で最も有名なのカジノの一つを所有していましたが、ある時全て売却してしまいました。その理由は何だったのでしょうか?
時は半世紀遡りますが、トランプ氏は東海岸のアトランティックシティに帝国を築き上げました。彼が建てたトランプ・タージマハルは瞬く間に盛況となり、彼は最も有名な東海岸の顔になりました。その後時は流れ、トランプ氏はウォール街で大きく成功することを決意します。アトランティックシティの時と同じくアメリカの金融市場を相手にまた大きく儲けようと目論んでいたわけですが、残念ながらその試みは失敗に終わりました。さて、東海岸でその当時何が起こったのでしょうか?
トランプ氏は東海岸のカジノおよびアトランティックシティが崩壊することを予測したのです。実際、カジノの経営状況はあまり芳しくありませんでしたが、彼の組織やチームは財務報告を隠蔽して多くのスポンサーを集めました。90年代初頭には、彼の所有するカジノの経営状態はかなりひどい状況に陥っていましたが、誰もそのことを知りませんでした。彼はカリスマ性のある経営者としてのイメージを利用して、自分たちが抱えている真の問題を隠し、ローンや貸付をかなり受けていました。多くの銀行がトランプ氏を相手に訴訟を起こしましたが、彼らが取り返すことができた金額は被害額よりも遥かに低いものでした。しかし、銀行は貸し出した全額を失うのを避けるために、低い金額でも受け取っていました。
経済的な観点から見ると、彼の帝国を破壊したのはトランプ・タージマハルだったと言えます。キャッスルやプラザが毎年のように閉鎖されていたのにも関わらず、誰もそのことに気づいていませんでした。トランプ氏が大量の借金をして損失を覆い隠していたからです。また、それと同じ時期に、彼は自らの不動産帝国でも損失を出し始めていました。しかし、当時は誰もそのことを知らず、人々はトランプ氏の経営する事業が近々破産するなど想像すらしませんでした。
今のトランプ氏は、その時期が彼の帝国にとって黄金期だったと語っていますが、実情は全く異なっていました。トランプ・タージマハルは1992年に破産裁判所の手続きを行っていました。プラザとキャッスルも似たような状況でした。この時期のトランプ帝国は大きな損失に悩まされていたのです。その上、景気後退が問題に拍車をかけました。ギャンブラーたちはアトランティックシティに疑念を抱き始め、「東のラスベガス」は顧客を徐々に失っていったのです。
アトランティックシティは彼が長年に渡ってミルクを絞り続けてきた仔牛のような存在でした。トランプ氏自身、アトランティックシティのおかげで大金を稼げたと語っています。しかし、問題はお金を儲けたのが彼だけだったことです。アトランティックシティが栄えたのは素晴らしいことでしたが、システム化することができなかったため、街の成長につながるはずのプロジェクトはことごとく失敗に終わったのです。
このような観点から見てみると、トランプ氏は小さな人間を踏み台にしてはしごを登っていたようです。しかし一番上までたどり着いた彼は、彼を現在の地位に押し上げるのに貢献してくれた人々をないがしろにしてきたのです。彼はとにかくあらゆる手段を講じました。最終的には自らが作った借金の多くを株主へと押し付けるなど、自らの黄金時代を続けていくためには手段を選びませんでした。
2000年代の初頭になると、トランプ氏は自身が抱えるさまざまな問題や多額の借金を隠し続けられなくなっていました。彼はチーフエグゼクティブを解雇し、大幅なリストラを行いました。しかし彼自身は依然として頂点に居続けました。その後、カジノが倒産寸前となったのは2009年のことで、彼が全てのカジノを他の経営者に売却する決断をしたのもその時でした。ところが、2009年以降も「トランプブランド」によって、自らの個性を生かしながら、彼は大金を儲け続けてきました。実際、カジノのシェアは2009年当時よりほとんど下がっていないので、彼は適切なタイミングでカジノを売却したことになります。